�~�Ɋւ��锽�]
�~�Ɋւ��锽�]�́A�����I�T�O�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A��������ł͋������Ă��Ȃ��̂ŁA���̊T�v�ɂ��Đ�������B
�P�D�~�Ɋւ��锽�]�Ƃ�
�u�~�Ɋւ��锽�]�v���邢�͗����āu���]�v�Ƃ́A���ʏ�̓_����_�ւ̎ʑ��ŁA���}�Ɏ������̂ł���B
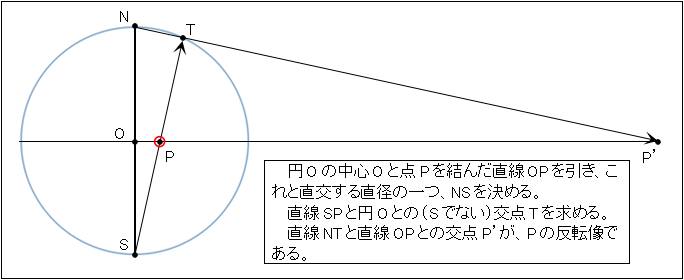
���̂Ƃ��A�u�_�o�́A�~�n�Ɋւ��锽�]�́A�_�o�f�ł���v�Ȃǂƌ����B
�܂��A�_�W���ł���}�`���̓_�̉~�n�Ɋւ��锽�]�̏W�����A�}�`���̉~�n�Ɋւ��锽�]�Ƃ����B
�܂���邱�Ƃ������ꍇ�́A�����́u�~�n�Ɋւ���v���A�ȗ�����B
�_�n�́A�~�n�Ɋւ��锽�]�́A���̒�`���@�ł͌��߂��Ȃ��B���̂��Ƃ������āA�u�~�̒��S�̔��]�͌��߂��Ȃ��v�Ƃ��闬�V�ƁA�u�~�̒��S�̔��]�́A�g�������_�h�Ɩ��Â���ׂ��A���E�ɂ�������̓_�ł���v�Ƃ��闬�V������B
�Q�D�u�L�`�̉~�v�ɂ���
�~�Ɋւ��锽�]�Ɋ֘A����T�O�̈�ł���A�u�L�`�̉~�v�Ɗ֘A���鏔�T�O�ɂ��ďq�ׂ�B
���@��`
�~���邢�͒����̂��Ƃ��A�u�L�`�̉~�v���邢�͗����āu�~�v�ƌ����B
�P�Ɂu�~�v�ƌ����ƍ����������\��������̂ŁA�ʏ�̉~�̂��Ƃ��A�u���`�̉~�v�ƌ������Ƃ�����B
��L�́u�g�������_�h�Ɩ��Â���ׂ��A���E�ɂ�������̓_�v���l���闬�V�ł́A�����́A�������_��ʂ�~�ł���ƍl����B
�������g�~�h�ł���Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�����Ɋւ��锽�]���l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���@��`
�����Ɋւ��锽�]�́A���̒����Ɋւ���Ώ̕ϊ��ł���B
���̒�`�͋��`�̉~�Ɋւ��锽�]�Ɛ������������Ƃ��A�e�Ղɕ�����B
�i���́u�e�Ղɕ�����v�́A�u�ؖ�����͔̂ς킵���̂ŏؖ����T�{��v�Ƃ����Ӗ��̐��w�җp��ł���B�K�������e�Ղł͂Ȃ��j
�~�ƒ������ꏏ�����ɂ��Ă��܂��̂ŁA�����Ɋւ���T�O�ł���u�p�v�ɂ��Ă���`����B
���@��`
�Q�̉~���Q�_�����L����Ƃ��A���̌��p�i���邢�͂Ȃ��p�j�Ƃ́A���̌�_�̈�ɂ�����ڐ��̌��p�̂��Ƃł���B
�Q�̉~�̌��p�����p�̂Ƃ��A�����̉~�͒�������ƌ����B
���̒�`�ł́A���`�̉~�Ƌ��`�̉~�̌��p�݂̂Ȃ炸�A���`�̉~�ƒ����Ƃ̌��p�ɂ��Ă��q�ׂĂ���B
���L����`�Ƃ��āA�u��_�Őڐ����l���邱�Ƃ̂ł���Q�Ȑ��̌��p�Ƃ́A��_�ɂ�����ڐ��̌��p�̂��Ƃł���v������B
�R�D�~�Ɋւ��锽�]�̏�����
���]�̏������ɂ��āA�ؖ������ɏq�ׂ�B
�@�@�_�o�́A�~�n�Ɋւ��锽�]���_�o�f�ł���Ƃ��A�_�o�f�́A�~�n�Ɋւ��锽�]�́A�_�o�ł���
�A�@�~�o�́A�~�n�Ɋւ��锽�]�́A�~���邢�͒����ł���B
�~�o���A�~�n�̒��S�n��ʂ�Ƃ��͒����ƂȂ�A�ʂ�Ȃ��Ƃ��͉~�ƂȂ�B
�B�@�������́A�~�n�Ɋւ��锽�]�́A�~�n�̒��S�n��ʂ�~�ł���B
�����A�ƇB���A�u�L�`�̉~�́A���`�̉~�n�Ɋւ��锽�]�́A�L�`�̉~�ł���B�v�Ƃ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B
����ɁA�����Ɋւ��锽�]�A���Ȃ킿�Ώەϊ��ł͐}�`�̌`�͕ς��Ȃ��̂ŁA�u�L�`�̉~�́A�L�`�̉~�Ɋւ��锽�]�́A�L�`�̉~�ł���B�v�ƌ�����B
���̂��Ƃ��A�u���]�́A�~�\�~�Ή��ł���v�A�u���]�́A���`�ϊ��ł���v�Ȃǂƌ����B�u���`�v�Ƃ́A�ϊ��O�ƕϊ��オ���ɉ~�Ƃ����A�����`�ł���Ƃ����Ӗ��ł���B
�C�@�Q�̉~�i��ʓI�ɂ͂Q�̋Ȑ��j�̌��p�̔��]���́A�����傫���̊p�ł���B���ɁA��������Q�~�̔��]���́A��������B
���̂��Ƃ��A�u���]�́A���p�ʑ��ł���v�Ȃǂƌ����B
�D�@�_�o�́A�~�n�Ɋւ��锽�]���_�o�f�ł���Ƃ��A�~�n�́A�_�o�o�f��ʂ�C�ӂ̉~�Ɋւ��锽�]�́A�~�n���g�ł���B
�E�@�_�o�́A�~�n�Ɋւ��锽�]���_�o�f�ł���Ƃ��A�_�o�o�f��ʂ�C�ӂ̉~�́A�~�n�ƒ�������B
�S�D�u�������_�v�̈�Ӑ��ɂ���
�u�������_�v�ƌĂ��T�O�́A�w�̑��̕���ɂ�����A���ɂ͕����̖������_�����݂�����̂�����B���Ƃ��Ύˉe�w�Łu�������_�v���邢�́u�����_�v�ƌĂ��_�́A�������݂���B�������A�����ł̖������_�́A���E�Ɉ�����ƍl����B����������ƁA���̐��E�ł́A�u�������_�v�Ƃ������t�́A���ʖ����ł͂Ȃ��A�ŗL�����ł���B
���̂��Ƃ́A�T�O���R�����ȏ�̍������Ɋg�����Ă��A���l�ł���B
�T�D�O�����ł̊֘A�����\���̎ˉe�ɂ���
���̎ˉe�́A���ʂ���P�_����菜�������̂ƕ��ʂƂ̈�Έ�Ή��̈�ł���A�ȉ��̂悤�ɒ�`����B
���@��`
���ʃ��ƕ��ʃ�������Ƃ��A���ʃ����畽�ʃ��ւ̗��̎ˉe�A����ѕ��ʃ����狅�ʃ��ւ̗��̎ˉe�B
�܂��A���ʃ��̒��S��ʂ�A���ʃ��ւ̐����������B
����Ƌ��ʃ��Ƃ̌�_�ŁA���ʃ���̓_�łȂ����̂̂P���m�Ƃ���B���̂m�𗧑̎ˉe�̋ɂƌ����B
���ʃ��̂m�ȊO�̓_�o�ɂ��āA�����m�o�ƕ��ʃ��Ƃ̌�_�o�f���A���ʃ����畽�ʃ��ւ̗��̎ˉe�œ_�o�ɑΉ�����_�Ƃ���B
���ʃ����畽�ʃ��ւ̗��̎ˉe�̋t�ʑ����A���ʃ����狅�ʃ��ւ̗��̎ˉe�ƌ����B
���̒�`�ł́A�_�m�͒��Ԃ͂���ł��邪�A�������_���l���闬�V�ł́A�_�m�ɑΉ�����_�͖������_�ł���Ƃ���B�������_�́A���E�ɂ�������ł���̂ŁA���̂悤�ɂ��Ă���Έ�Ή��ƂȂ��Ă���B
���ʃ��ɂ�����m�̑��G�_���r�Ƃ���B�ɂm����ӂłȂ��Ƃ��A���Ȃ킿���ʃ��ƕ��ʃ�������邩����Ă���Ƃ��A�_�r���A���ʃ����狅�ʃ��ւ̗��̎ˉe�̋ɂƂȂ蓾��B
�����ŁA�_�r���ɂƂ��镽�ʃ����狅�ʃ��ւ̗��̎ˉe���s���A�����������ʃ����畽�ʃ��ւ̗��̎ˉe���ɂ��m�Ƃ��čs�����Ƃɂ��A���ʃ���̎ʑ���������B���̎ʑ��́A���ʃ��ƕ��ʃ��������Ƃ��́A���ʃ��ƕ��ʃ��������̉~�Ɋւ��锽�]�ƂȂ�B���ʃ��ƕ��ʃ�������Ă���Ƃ��́A���]�ł͂Ȃ��������ɒ�������R�~�Ɋւ��锽�]�R�������������̂ɂȂ�B
���̎ˉe�́A�~�\�~�Ή��ł���A���p�ʑ��ł���B���ʏ�̒����ɂ͋��ʏ�̋ɂ�ʂ�~���A���ʏ�̋��`�̉~�ɂ͋��ʏ�̋ɂ�ʂ�Ȃ��~���Ή�����B
�U�D�O�����ł̋��A�~�A�_�Ɋւ��锽�]
���@��`
���܂��͕��ʂ̂��Ƃ��A�u�L�`�̋��v���邢�͗����āu���v�ƌ����B���ʂłȂ������A�u���`�̋��v�ƌ����B
�_�܂��͓_�̂��Ƃ��A�u�L�`�̓_�v���邢�͗����āu�_�v�ƌ����B��_�łȂ��_���A�u���`�̓_�v�ƌ����B
���@��`
���`�̋��Ɋւ��锽�]���A���`�̉~�Ɋւ��锽�]�ɏ����Ē�`����B���̂Ƃ��A�u�~�v�́u���v�ɓǂݑւ���B
�L�`�̋��Ɋւ��锽�]���A�L�`�̉~�Ɋւ��锽�]�ɏ����Ē�`����B���̂Ƃ��A�u�~�v�́u���v�ɁA�u�����v�́u���ʁv�ɓǂݑւ���B
���Ɖ~�̌��p�A���Ƌ��̌��p���A�~�Ɖ~�̌��p�ɏ����Ē�`����B���̂Ƃ��A�u�~�v�A�u�����v�́A�K�X�u���v�A�u���ʁv�ɓǂݑւ���B
���@��`
��Ԃɂ�����~�Ɋւ��锽�]���A���̉~�������Ƃ���A�������ɒ�������Q���Ɋւ��锽�]�̍����ɂ���`����B
���̂Ƃ��A�Q���̑I�ѕ�����э����̏����̈Ⴂ�ɂ�炸�A��ӂɊm�肷��B
��Ԃɂ�����_�̊ւ��锽�]���A���̓_�������Ƃ���A�������ɒ�������R���Ɋւ��锽�]�̍����ɂ���`����B
���̂Ƃ��A�R���̑I�ѕ�����э����̏����̈Ⴂ�ɂ�炸�A��ӂɊm�肷��B