【問1】【問2】に関して、nの値にかかわらず言えること、その他関係ありそうなことがら
ここには、「もしかしたら正解に近づけるかもしれないこと」を書きます。
![]() 点は、3つの頂点すべてに配置されるとしてよいということ
点は、3つの頂点すべてに配置されるとしてよいということ
【問1】はn≧1、【問2】はn>1という条件なので、少なくとも3点は配置されると考えてよい(実際、【問1】の場合は3点以上、【問2】の場合は4点以上である)。
そのうちの3点が3つの頂点にあるとしてよい、あるいは「頂点に点が配置されていなければ、どれかの点を頂点に移動させても、題意に反しない」と言い換えた方がわかりやすいだろうか。
【証明】
正三角形ABCの頂点Aに、点が配置されず、かつ題意を満たす配置があったとする。
そのとき、頂点Aの対辺BCから最も遠い点をPと名づける。
Pを通る、BCと平行な直線をB’C’とする。点B’、点C’は、この直線と辺AB、辺ACとの交点である。
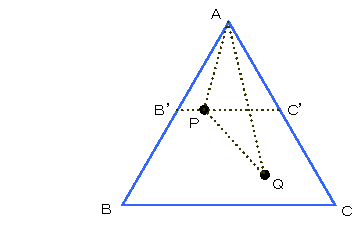
P点をAに移動させても、題意を満たすことを示す。
そのためには、P以外の配置された任意の点QとAとの距離は、Pの元の位置とQとの距離を下回らないことを言えばよい。
△AB’Pで、∠B’≦∠APC’、∠B’=60°。
また、∠APC’≦∠APQ。
ゆえに、∠APQ≧60°。
△APQで、∠PAQ≦60°なので、∠PAQ≦∠APQ。
したがって、PQ≦AQ。
■
![]() 正三角形の各辺のn分点どうしを結ぶことによって、辺長が1/nの、n2個の小正三角形に分けることができるが、n≧4のときは、これらの小正三角形の頂点がどの小正三角形に属するかを決めて、どの小正三角形についても、高々1点しか頂点を含まないようにできる。
正三角形の各辺のn分点どうしを結ぶことによって、辺長が1/nの、n2個の小正三角形に分けることができるが、n≧4のときは、これらの小正三角形の頂点がどの小正三角形に属するかを決めて、どの小正三角形についても、高々1点しか頂点を含まないようにできる。
【証明】
n=4のときは、たとえば、下図。
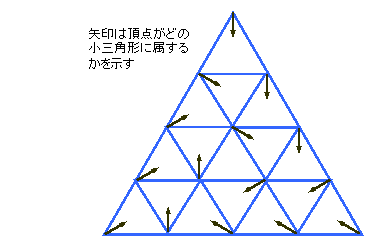
n>4のとき、もしn=kで言えれば、k+1でも言えることを示す。
k分割したものを、k/(k+1)倍して、上に詰めれば、一番下に並ぶ小正三角形(上向きも下向きもある)以外について、頂点の所属が決められる。
一番下に並ぶ小正三角形のうち、上向きの両端のものには、下の正三角形の頂点を割り振る。
その他の上向きのものには割り振らない。
下向きのものには、下端の頂点を割り振る。
これで、条件を満たす頂点の割り振りの一例ができた。
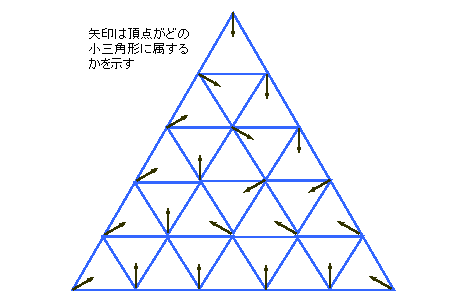
■
![]() 半径rの円内(周上を含む)に、互いの距離がrより大きくなるように複数の点を配置すると、これらの点の凸包の頂点以外には、点は配置されない。
半径rの円内(周上を含む)に、互いの距離がrより大きくなるように複数の点を配置すると、これらの点の凸包の頂点以外には、点は配置されない。
【証明】
この円の中心には、点が配置されないことは明らか。
ひとつの点Aと円の中心とを結ぶ線分の垂直二等分線を引くと、点A以外の点は、すべてこの直線について、Aと反対側にある。
このことは、点Aを中心として、半径rの円を描くと、点A以外はこの円の外側にあることから分かる。
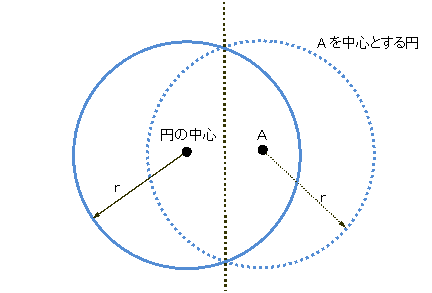
さらに、この直線と平行な、点Aを通る直線を引くと、点A以外の点はすべて、この直線の一方の側(円の中心がある側)にある。
このことは、点Aは、凸包の頂点である。
■
このことから、円内(周上を含む)に辺長が円の半径より大きい多角形を置くと、必ず凸多角形であることが分かる。
「円内(周上を含む)」としたが、「周上を含まない」とした場合は、「rより大きく」の代わりに「r以上に」とすれば、同様のことが言える。
円に内接する正六角形は、辺長が円の半径に一致し、この円に含まれるので、円の代わりに正六角形、円の半径の代わりに正六角形の辺長とすれば、同様なことが言える。