【問3】で(n+D)!/(n!・D!)個の点が配置できること
【問3】の条件で、(n+D)!/(n!・D!)個の点が配置できることを、(D+1)次元ユークリッド空間を考えることによって示す。
(D+1)次元ユークリッド空間における、正規直交座標系の各座標軸上の1/(√2)の点(全部でD+1個ある)を通るD次元超平面の、どの座標値も負でない点全体は、一辺が1のD次元正三角錐となる。しかし、いちいち「√」などを書くのはわずらわしいので、(n√2)倍して、各座標軸のnの点を頂点とするD次元正三角錐を考える。この正三角錐の点の座標は、座標値を合計するとnになっている。
この、一辺が(n√2)の正三角錐の点で、座標値が整数のものを考え、その位置に点を配置すれば、(1/(n√2)倍して)条件に合った配置となることを示せばよい。
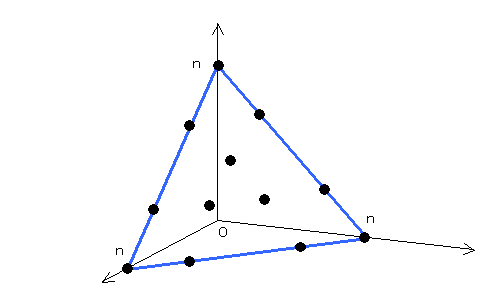
まず、距離を考える。
異なる2点間の距離の2乗は、ピュタゴラスの定理を用いて、対応する座標値の差の平方の和であることが分かる(と言うか、これをD次元ユークリッド空間の距離の定義とするのが普通である。「2乗」と書いたり「平方」と書いたり不統一だが、私の感覚ではこうなる)。
ここで、配置された2点間の距離の2乗を考える。
異なる2点を考えているので、少なくとも1つの座標値は異なる。しかも整数なので、その差は1以上であり、その平方も1以上である。
また、「座標値を合計するとnになっている。」という条件があるので、さらに少なくとも1つ、座標値が異なっている。もちろん、その差も1以上、その平方も1以上である。
したがって、平方の和は、2以上になる。このことから、距離は√2以上であることが分かる。
(n√2)倍していたので、本来の距離にすれば、1/n以上となる。
次に、配置された点の個数を数える。
これが(n+D)!/(n!・D!)個となることは、数学的帰納法を2重に適用することによって明らかとなる。
Q.E.D.■
ちなみに、(n+D)!/(n!・D!)は、組み合わせの記号を用いて、(n+D)Cn、(n+D)CDなどと表せる。しかし、今のところ、私には組み合わせ論とのかかわりは、これ以上分からない。
Dについての数学的帰納法を用いて示すことも考えたが、文章にしたり図解したりすると、意外と大変なのでやめた。しかし、せっかく考えかけたことなので、途中まで書いたり描いたりしたものを、ここに残しておく。
Ⅰ.まず、D=1なら、すべてのnで成り立つことを示す。
Ⅱ.次に、D=kで成り立つなら、D=k+1でも、すべてのnで成り立つことを示す。
Ⅲ.上記Ⅰ.、Ⅱ.により、すべてのDについて、すべてのnで成り立つことが言える。
Ⅰ.まず、D=1なら、すべてのnで成り立つことを示す
D=1ということは、長さ1の線分ということである。
1/n分点、すなわち、一方の端点から、0/n、1/n、2/n、…、(n-1)/n、n/nの距離の位置に配置すれば、隣の点までの距離は1/n、それ以外の点までの距離はその倍数なので、いずれも1/n以上となる。
このときの点の個数は、n+1である。これは、(n+1)!/(n!・1!)に一致する。
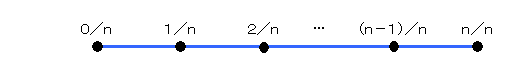
Ⅱ.次に、D=kで成り立つなら、D=k+1でも、すべてのnで成り立つことを示す
(k+1)次元正三角錐の、1頂点とその対面との間をn等分する。n個のブロックができるが、その各ブロックの底面は、k次元正三角錐である。その、頂点側から数えてp番目のものの、「1/p分点」に配置する。「1/p分点」とは、このようにして決めた点のことである。k次元ではこのようにしてすでに決まっているので、(k+1)次元で、このようにして決めることができる。
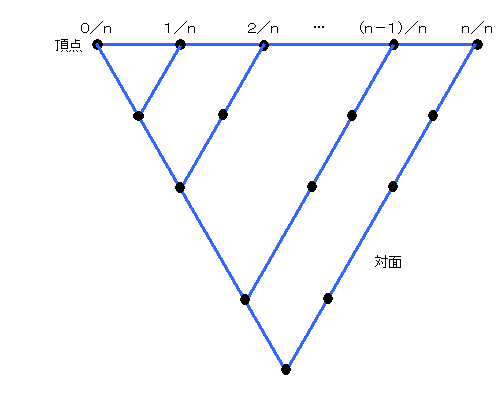
これらの底面内の各点間の距離は、高々1/nであることはすぐ分かる。
異なる底面にある2点間は、…ここで挫折しました。