【問1】(〜以上〜)
【解】kの最大値は6(=(n+1)(n+2)/2)である。
6点が可能であることはすでに言えているので、7点が不可能であることを言う。
正三角形の各辺の中点どうしを結ぶことによって、辺長が1/2の、4つの小正三角形に分けることができる。このとき、境界がどの小三角形に属するかを厳密に決める。
具体的には、中央の小三角形は境界を持たないもの(開三角形)とし、各辺の中点は、時計回りに見て前方の小三角形に属するものとする。中央以外の小三角形は、閉三角形から1頂点を除いたものになる。
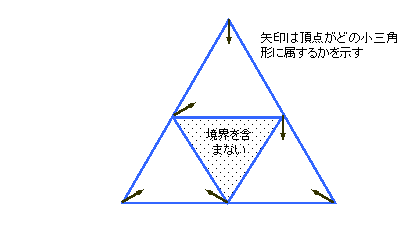
このようにすると、中央の小三角形には2点を配置することはできない。なぜなら、三角形に含まれる2点の距離がその三角形の最大辺の長さのときは、この2点はこの三角形の頂点に無ければならない(「【問3】【問4】は、n=1のときは完全に解けること」の付記参照)のに、この小三角形は頂点を含んでいないから。
また、他の小三角形には、3点を配置することはできない。なぜなら、これらの小三角形は、頂点を2つしか含んでいないから。
こうして、配置すべき7点は、中央の小三角形内に1点、他の小三角形内に2点ずつとなる。
このとき、「他の小三角形」には2頂点に配置されることになるが、その一方は、元の閉三角形の辺の中点である。この点は、中央の小三角形にとっては、属してはいないが、頂点である。
したがって、中央の小三角形にとっては、内部の1点と、頂点とが見えることになる。
しかし、内部の点と頂点との距離は、最大辺の長さより短い(「【問3】【問4】は、n=1のときは完全に解けること」のD=2のときの、dから類推してください)。
最大辺の長さは1/2であるから、これは、題意に反する。
■
【問2】(〜より大〜)
【解】kの最大値は4(=(n+1)(n+2)/2−2)である。
まず、4点が可能であることを言う。
たとえば、正三角形の各頂点と中央(重心)に配置すればよい。
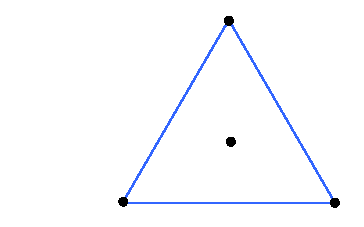
次に、5点が不可能であることを言う。
正三角形の各辺の中点どうしを結ぶことによって、辺長が1/2の、4つの小正三角形に分けることができる(境界は共有することにする)。

もし5点を配置することができれば、4つの小三角形の少なくとも1つはそのうちの2点を含む(鳩の巣原理)。
ところが、三角形に含まれる2点の距離は、その三角形の最大辺の長さを超えることはできない(「【問3】【問4】は、n=1のときは完全に解けること」の付記参照)。
これは、題意(距離は1/2より大)に反する。
■