�����ł́A�������̓����T�C�Y�̕��O�p�`���A�Ȃ��Ă���Ƃ��A���̒��ɁA���̐��O�p�`�̕ӈȏ�̋�����u���Ĕz�u�����_���A�ǂ̂悤�Ȉʒu�W�ɂȂ邩�ɂ��Č�������B
���Ƃ��Ή��}�̏ꍇ�A�u�o�p���`�a�Ȃ�A�o�a���p�b�ƂȂ�A�o�a���p�b�ƂȂ�̂͂o�p���`�a�̂Ƃ��Ɍ���B�v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���B

�藝�P�F��}�i�o�́��`�a�b��A�p�́��`�a�f�b��j�ŁA�o�p���`�a�Ȃ�A�o�a���p�b�ƂȂ�B�o�a���p�b�ƂȂ�̂͂o�p���`�a�̂Ƃ��Ɍ���A�o�͕ӂ`�a��łp�͕ӂa�f�b�ォ�A���邢�͂o���b�łp���`�ł���B
�ؖ��F
�ꍇ�������čl����B
���F�o���`
���F�o���a
���F�o���b
���F�o�͕ӂa�b���A�p�͕ӂa�f�b��
���F�o�͕ӂa�b���A�p�͕ӂ`�a�f��
���F�o�͕ӂa�b���A�p�́��`�a�f�b��
���F�o�͕ӂ`�a���A�p�͕ӂa�f�b��
���F�o�͕ӂ`�a���A�p�͕ӂ`�a�f��
���F�o�͕ӂ`�a���A�p�́��`�a�f�b��
���F�o�́��`�a�b���A�p�͕ӂa�f�b��
���F�o�́��`�a�b���A�p�͕ӂ`�a�f��
���F�o�́��`�a�b���A�p�́��`�a�f�b��
���F�o�͕ӂ`�b��
����ł��ׂĂ̏ꍇ��ԗ����Ă���͂��ł���B
�p�́A�a�f�A���邢�͂b�ȊO�ɂ͂��肦�Ȃ��i�O�p�`�̍Œ��ӈȏ㗣�ꂽ�Q�_�́A���̍Œ��ӂ̗��[�_�ł���F�u�y��R�z�y��S�z�́A�����P�̂Ƃ��͊��S�ɉ����邱�Ɓv�̕t�L�Q�Ɓj�B
�ǂ���̏ꍇ���A���肪�^�ł��邱�Ƃ͖��炩�B
����ɁA�p���b�ƁA�p���b�Ƃɕ�������B�ǂ���̏ꍇ�����炩�B
��L���Ɠ��l�B���肪�^�ł��邱�Ƃ͖��炩�B
����Ɗw�炵���Ȃ�B
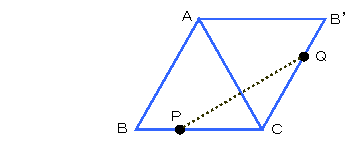
��}�ŁA�o�p���a�b�i��Ӂj�B
�܂��A�o�b�{�b�p���o�p�i�O�p�s�����j�B
�a�b���a�o�{�o�b�i�o�͕ӂa�b���j�B
����炩��A�o�b�{�b�p���a�o�{�o�b�B
�䂦�ɁA�b�p���a�o�B
���ӁF���̋c�_�́A�p���ӂa�f�b�́A�a�f���̉�����ɂ����Ă����藧�B
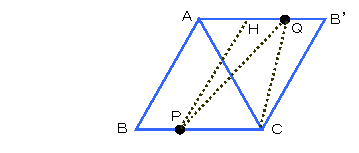
��}��H�́A�`�g���a�o�ƂȂ�_�Ƃ���B
�o�p���`�a�Ȃ̂ŁA�`�p���`�g�B
���̂��Ƃ́A�`�p���`�g�Ƃ���ƁA���̂悤�ɖ������������̂ŕ�����B
�`�p���`�g�Ƃ���ƁA�p�́��`�o�g�̕ӂ`�g���̓_�ł���B����ƁA�o�p�́A���`�o�g�̍Œ��ӈȉ��ł���A�Œ��ӂɒ�������v����Ƃ��́A�o�p���Œ��ӂƂȂ�B
�Ƃ��낪�A�`�o���`�a���o�g�A���`�g���`�a�f���o�g�Ȃ̂ŁA���`�o�g�̍Œ��ӂ͂o�g�ł���i�������B��̍Œ��ӂł���j�B���������āA�o�p���o�g�B
�������A�o�p���`�a���o�g�Ȃ̂ŁA�o�p=�o�g�łȂ���Ȃ�Ȃ��B����ƁA�o�p�͗B��̍Œ��ӂo�g�ƒ[�_����v���A�p���g�ƂȂ�B
����́A�`�p���`�g�ɔ�����B�i�u�o�p���`�a�Ȃ�A�`�p���`�g�v�̏ؖ��I���j
���āA���`�b�p�ŁA�ڂ`���ڂb�Ȃ̂ŁA�p�b���`�p�B
���������āA�p�b���`�g���o�a�B
���F�o�͕ӂa�b���A�p�́��`�a�f�b��
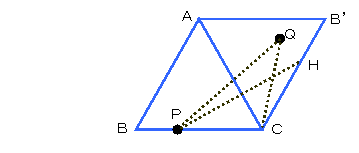
H�́A�o�g���o�p�ƂȂ�A�a�f�b��̓_�ł���B
�o�𒆐S�ɂ��āA���a���o�p�̉~��`���ƁA�b�͂��̓����̓_�A�a�f�͂��̊O���̓_�Ȃ̂ŁA���̂悤�Ȃg�͕K�����݂���B
�b�����̉~�̓����ł��邱�Ƃ́A�o�b���`�a���o�p���猾����B
�a�f�����̉~�̊O���̓_�ł��邱�Ƃ́A�p�����`�o�a�f���A���o�b�a�f���̏��Ȃ��Ƃ�����ɑ����A�ǂ���̎O�p�`���Œ��ӂ��o�a�f�ł��邱�Ƃ��猾����i���Ƃ��A���`�o�a�f�ł`�a�f���o�a�f�́A�ڂo���U�O�K�A�ڂ`���U�O�K�ƂȂ�̂ŕ�����j�B
�o�g���o�p�Ȃ̂ŁA�o�g���`�a�B
���������āA��L���ɂ��A�b�g���a�o�B
�܂��A�ڂg�p�b���ڂg�p�o���ڂp�g�o���ڂp�g�b�Ȃ̂ŁA�b�p���b�g�B
����āA�b�p���a�o�B
���ӁF���̋c�_�́A�p�����`�a�f�b�̊O���ɂ����Ă��APQ���o�a�f�A �b�p���b�g��������A���藧�B�������A�b�p���b�g�������Ă��܂��B
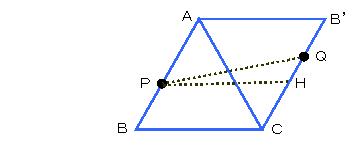
�g�́A�ӂa�f�b��ŁA�b�g���a�o�ƂȂ�_�ł���B
��L���ɂ�����Ɠ��l�ȋc�_�ŁA�b�p���b�g���a�o�ł��邱�Ƃ�������B
�b�p���b�g�ƂȂ�Ƃ��́A�l�p�`�o�a�b�p�����s�l�ӌ`�ƂȂ�Ƃ��ł���A�o�p���a�b���`�a�ł���B
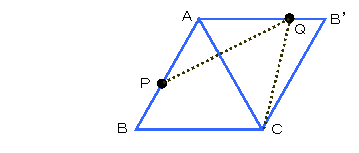
��L���ł`�Ƃb�̖��������ւ���A�`�p���a�o��������B
���`�p�b�ɂ����āA�ڂ`���ڂb�Ȃ̂ŁA�b�p���`�p�B
���������āA�b�p���a�o�B
���F�o�͕ӂ`�a���A�p�́��`�a�f�b��
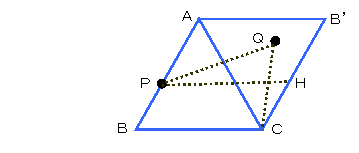
�g�́A�ӂa�f�b��ŁA�o�p���o�g�ƂȂ�_�Ƃ���B
��L���Ɠ��l�ȋc�_�ŁA���̂悤�Ȃg�����݂��邱�Ƃ�������B
��L������A�g�b���o�a�B
�Ă���L���Ɠ��l�ɁA�p�b���g�b�B
����炩��A�b�p���a�o�B
���F�o�́��`�a�b���A�p�͕ӂa�f�b��
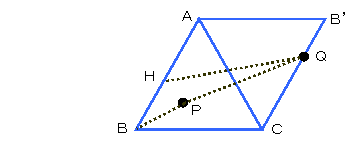
�ӂ`�a��ŁA�a�g���a�o�ƂȂ�_�g���Ƃ�B
���o�p�g�ŁA�ڂg���ڂo�g�`���i�ڂg�o�a�̕�p�j���ڂo�Ȃ̂ŁA�g�p���o�p�B���������āA�g�p���`�a�B
����ƁA��L������A�b�p���a�g�B�a�g���a�o�Ȃ̂ŁA�b�p���a�o�B
���F�o�́��`�a�b���A�p�͕ӂ`�a�f��

�ӂa�b��ŁA�a�g���a�o�ƂȂ�_�g���Ƃ�B
���o�p�g�ŁA�ڂg���ڂo�g�b���i�ڂg�o�a�̕�p�j���ڂo�Ȃ̂ŁA�g�p���o�p�B���������āA�g�p���`�a�B
����ƁA��L������A�b�p���a�g�B�a�g���a�o�Ȃ̂ŁA�b�p���a�o�B
���F�o�́��`�a�b���A�p�́��`�a�f�b��
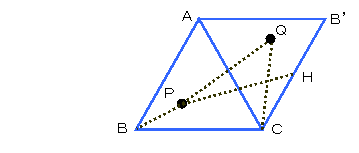
�ӂa�f�b��ɁA�o�g���o�p�ƂȂ�_���Ƃ�B
��L���Ɠ��l�ȋc�_�ŁA���̂悤�Ȃg���Ƃ�邱�Ƃ�������B
���p�b�g�ŁA�ڂp���ڂo�p�g���ڂo�g�p���ڂg�Ȃ̂ŁA�p�b���g�b�B
�܂��A��L���ɂ��A�g�b���a�o�B���������āA�p�b���a�o�B
���ӁF��L���Ɠ��l�A���̋c�_�́A�p�����`�a�f�b�̊O���ɂ����Ă��APQ���o�a�f�A�p�b���g�b��������A���藧�B�������A�p�b���g�b�������Ă��܂��B
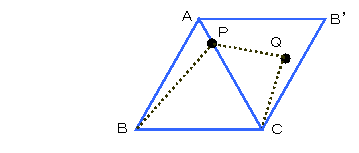
����͂��肦�Ȃ��B�o�p���`�a���i���`�a�f�b�̍Œ��Ӂj�ł��邪�A��������Ƃo�́��`�a�f�b�̒��_�łȂ���Ȃ�Ȃ�����B
��
�藝�Q�F�U�̐��O�p�`�����}�̂悤�ɐ��Z�p�`�ɕ��ׂ����̂ɁA�U�_���A�������ɂ����̐��O�p�`�̕Ӓ��ȏ�ɗ���Ĕz�u����ƁA���ׂĂ̓_���A�����̂ǂꂩ�̐��O�p�`�̒��_�ɂȂ�B
���������āA�������ɂ����̐��O�p�`�̕Ӓ���藣���Ĕz�u����ƁA�T�_�����z�u�ł��Ȃ��B
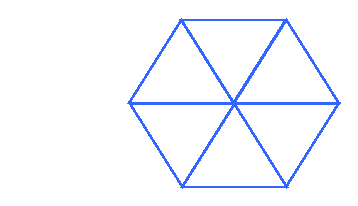
�ؖ��F
�ꍇ�������čl����B
���F���Z�p�`�̒��S�ɓ_��z�u����
���F���Z�p�`�̒��S�ɓ_��z�u���Ȃ�
���Z�p�`�̒��S�ɓ_��z�u���Ă��܂��ƁA���̓_����u���O�p�`�̕Ӓ��ȏ㗣�ꂽ�_�v�́A���Z�p�`�̒��_�����Ȃ��Ȃ�B
���������āA�藝�͐��藧�B
���F���Z�p�`�̒��S�ɓ_��z�u���Ȃ�
���O�p�`�̊e���_�̏����m�ɂ���B��̓I�ɂ͉��}�B�ӂ̏���������ɏ�����B
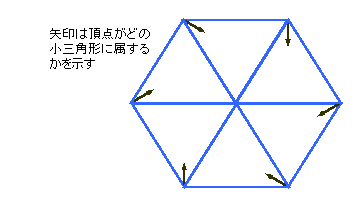
���S�́A�_��z�u���Ȃ��̂ŁA�������B
���̂悤�ɂ���ƁA�e���O�p�`�́A���傤�ǂЂƂ����_�������ƂɂȂ�B
���������āA�e���O�p�`�ɂ́A�Q�ȏ�̓_��z�u���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�e���O�p�`�ɂ́A���傤�ǂЂƂ��̓_��z�u���邱�ƂɂȂ�B
�����ł܂��ꍇ��������B
���|���F���鐳�O�p�`�ɒ��ڂ���ƁA���̒��_�i���Z�p�`�̒��_�j�ɓ_���z�u�����
���|���F���鐳�O�p�`�ɒ��ڂ���ƁA���̕Ӂi���Z�p�`�̒��S�ƒ��_�����Ԃ��́j���ɓ_���z�u�����
���|���F���鐳�O�p�`�ɒ��ڂ���ƁA���̕Ӂi���Z�p�`�̕Ӂj���ɓ_���z�u�����
���|���F���鐳�O�p�`�ɒ��ڂ���ƁA���̓����ɓ_���z�u�����
����ŁA���Z�p�`�̒��S�ɔz�u���Ȃ��ꍇ�̂��ׂĂ̏ꍇ��ԗ����Ă���B
���|���F���鐳�O�p�`�ɒ��ڂ���ƁA���̒��_�i���Z�p�`�̒��_�j�ɓ_���z�u�����
���v���ɉ���āA���̐��O�p�`�i�s�ƌĂԂ��Ƃɂ���j�̌��ɂ��鐳�O�p�`�i�r�ƌĂԂ��Ƃɂ���j���l����B
���O�p�`�s�ɔz�u���ꂽ�_����A���O�p�`�̕Ӓ��ȏ㗣�ꂽ�_�́A���O�p�`�r�ɂ́A���O�p�`�r�ɑ����钸�_�����Ȃ��B
���������āA���O�p�`�r���A���̒��_�ɓ_���z�u�����B
�ȉ��A���Ɍ��̐��O�p�`�ɂ��Ă��A���̒��_�ɓ_���z�u����邱�ƂɂȂ�A���ǂ��ׂĂ̓_���A�ǂꂩ�̐��O�p�`�̒��_�ɂȂ�B
�藝�͐��藧���Ă���B
���ӁF���̂Ƃ��A�_�Ԃ̋����̍ŏ��l�́A���O�p�`�̕Ӓ��ɓ������B
���|���F���鐳�O�p�`�ɒ��ڂ���ƁA���̕Ӂi���Z�p�`�̒��S�ƒ��_�����Ԃ��́j���ɓ_���z�u�����
����́A���肦�Ȃ��B
�Ȃ��Ȃ�A���̐��O�p�`�̌��̐��O�p�`��ɁA���̓_���琳�O�p�`�̕Ӓ��ȏ㗣�ꂽ�_�͑��݂��Ȃ�����B�e���O�p�`�ɂ��傤��1���̓_��z�u���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
���|���F���鐳�O�p�`�ɒ��ڂ���ƁA���̕Ӂi���Z�p�`�̕Ӂj���ɓ_���z�u�����
������A���肦�Ȃ��B
���}�̂悤�ɁA�e�_�ɖ��O�����邱�Ƃɂ���B���̐}�ł́A���ׂĂ̓_���ӓ��ɔz�u����Ă��邩�̂悤�ɕ\����Ă��邪�A���̂Ƃ���ɔz�u���ꂽ�_�������Ă��c�_�̖{���͕ς��Ȃ��B
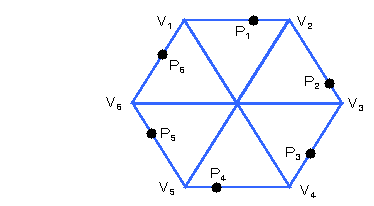
�o�P�`�o�U�͔z�u���ꂽ�e�_�A�u�P�`�u�U�́A���_�ł���B�Ή�������̂ɂ́A�����Y������t�����B���ڂ����O�p�`�̂��̂̓Y�����͂P�Ƃ����B
�藝�P����A�u�P�o�P���u�Q�o�Q���u�R�o�R���u�S�o�S���u�T�o�T���u�U�o�U���u�P�o�P�ƂȂ�B
���̓����t�s������̍ŏ��ƍŌ�͓������̂ł��邩��A���ׂē����l�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�藝�P�œ����l�ɂȂ邽�߂ɂ́A�o�P�͂u�P�ƒ��S�����ԕӏ�ɂ��邩�A�u�Q�Ɉ�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����́A�o�P�����O�p�`�̕Ӂi���Z�p�`�̕Ӂj���Ƃ�������ɔ�����B
���|���F���鐳�O�p�`�ɒ��ڂ���ƁA���̓����ɓ_���z�u�����
������A���肦�Ȃ��B
���}�̂悤�ɁA�e�_�ɖ��O�����邱�Ƃɂ���B���̐}�ł́A���ׂĂ̓_�����O�p�`�����ɔz�u����Ă��邩�̂悤�ɕ\����Ă��邪�A���̂Ƃ���ɔz�u���ꂽ�_�������Ă��c�_�̖{���͕ς��Ȃ��B
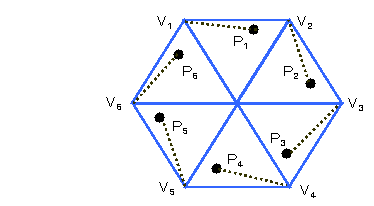
�o�P�`�o�U�͔z�u���ꂽ�e�_�A�u�P�`�u�U�́A���_�ł���B�Ή�������̂ɂ́A�����Y������t�����B���ڂ����O�p�`�̂��̂̓Y�����͂P�Ƃ����B
�藝�P����A�u�P�o�P���u�Q�o�Q���u�R�o�R���u�S�o�S���u�T�o�T���u�U�o�U���u�P�o�P�ƂȂ�B
���̓����t�s������̍ŏ��ƍŌ�͓������̂ł��邩��A���ׂē����l�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�藝�P�œ����l�ɂȂ邽�߂ɂ́A�o�P�͂u�P�ƒ��S�����ԕӏ�ɂ��邩�A�u�Q�Ɉ�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����́A�o�P�����O�p�`�̓����Ƃ�������ɔ�����B
��
�藝�Q�̌n�P�F�������̓����傫���̐��O�p�`���A�������ɕӂŐڂ��Ă��āA���ɂ��ǂ��Ă����ƌ��ɖ߂��悤�ɂȂ��Ă���Ƃ��A�����̐��O�p�`�Ɠ������̓_���������ɂ����̐��O�p�`�̕Ӓ��ȏ�ɗ����Ĕz�u���A�ׂ̐��O�p�`�Ɛڂ��Ă���ӂɂ͍��X�P�̓_�����z�u���Ȃ��悤�ɂ��A�ӏ�̓_�͂ǂ���̐��O�p�`�ɏ������邩�m�ɂ��āA�e���O�p�`�ɂ͂��傤�ǂP�_�����z�u�����悤�ɂ����Ƃ��A�z�u���ꂽ���ׂĂ̓_�́A�ǂ�������̂ǂꂩ�̐��O�p�`�̒��_�ɔz�u����A�_�ԋ����̍ŏ��l�͐��O�p�`�̕Ӓ��Ɉ�v����B
�ؖ��F
���̏����̏ꍇ�A�藝�Q�̏ؖ��������|�����邢�����|���ɂ�����s������Ɠ��l�ȓ����t�s���������邱�Ƃ��ł��A�ŏ��ƍŌオ�������̂ɂł���̂ŁA���̊e���̒l�͂��ׂē����ɂȂ�B���̂Ƃ��́A�_�ԋ����̍ŏ��l�͐��O�p�`�̕Ӓ��Ɉ�v����B
����ƁA���鐳�O�p�`�ɔz�u���ꂽ�_�́A���̒��_�ɂ��邩�A����ӓ��ɂ����ėׂ̐��O�p�`�̓_�Ƃ����ԂƂ����P�ӂƕ��s�ł���B
�O�҂̏ꍇ�A���̓_�͂Q����͂��ׂ̗̐��O�p�`�̏��Ȃ��Ƃ�����ɂƂ��Ă����_�ł���A���́u�ׂ̐��O�p�`�v�ɔz�u�����_���A���_�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B������܂����Ηׂ̐��O�p�`�ɂƂ��Ē��_�ƂȂ�A�ȉ����l�ɂ��ď����ׂ̐��O�p�`�̒��_�ɔz�u����Ă���A���������āA���ׂĂ̓_�����_�ɔz�u����Ă��邱�Ƃ�������B
��҂̏ꍇ�A�ׂ̐��O�p�`�ɔz�u���ꂽ�_���A���̐��O�p�`�̂���ӓ��ɂȂ邪�A���̕ӂ�����ɗׂ̐��O�p�`�Ƃ̋��E�ӂł���A���́u����ɗׂ̐��O�p�`�v�ɂ͓_�͔z�u�ł����A���E�ӂłȂ���ΐ��O�p�`�̓W�O�U�O�ɘA�Ȃ��Ă��������ŁA�u���ɖ߂��悤�ɂȂ��Ă���v�Ƃ������������Ȃ��i���}�j�B
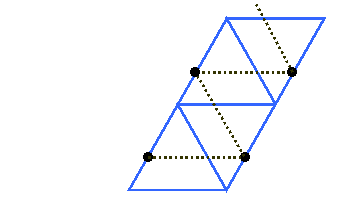
��
�藝�R�F���}�i�o�́��`�a�b��A�p�́��`�a�f�b��j�ŁA�o�p���`�a�A�o�`�C�b�p���o�o�C�p�p�Ȃ�A�o�a�{�p�a�f���`�a�B�o�a�{�p�a�f���`�a�ƂȂ�̂́A�o�p�a�`�a���邢�͂o�p�a�a�b�̂Ƃ��ł���i�u�a�v�́A��v����ꍇ���܂ށj�B
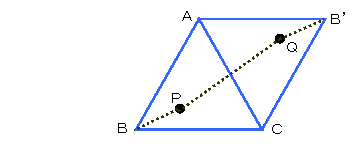
�ؖ��F
�ꍇ�������čl����B
���F�p���ӂa�f�b��
���F�p���ӂ`�a�f��
���F�p���ӂa�f�b��A�ӂ`�a�f��ȊO�ŁA�o�A�p�A�a�f�͓��꒼����
���F�p���ӂa�f�b��A�ӂ`�a�f��ȊO�ŁA�p�Ƃ`�́A�����o�a�f�̓�����
���F�p���ӂa�f�b��A�ӂ`�a�f��ȊO�ŁA�p�Ƃb�́A�����o�a�f�̓�����
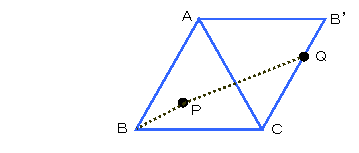
�藝�P�i���A���A���A���A�����邢�����̃P�[�X�j����A�o�a���p�b�B
�p�͕ӂa�f�b��Ȃ̂ŁA�a�f�p�{�p�b���a�f�b���`�a�B
����炩��A�o�a�{�p�a�f���`�a�i�����͂o�a���p�b�̂Ƃ��j�B
�藝�P�ŁA�o�a���p�b�ƂȂ�̂́A�o�p�a�a�b���A�o���b�i���̂Ƃ��͂p���a�f�Ȃ̂ło�p�a�`�a�j�̂Ƃ��ł���B
��L���ɂ����āA�_�`�Ɠ_�b�����ւ���悢�B
���F�p���ӂa�f�b��A�ӂ`�a�f��ȊO�ŁA�o�A�p�A�a�f�͓��꒼����
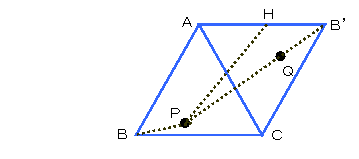
�_�g���A�a�f�g���a�f�p�ƂȂ�悤�ɁA�ӂ`�a�f��ɂƂ�B
���o�p�g�ɂ����āA�ڂp���i�ڂa�f�p�g�̕�p�j���i�ڂa�f�g�p�̕�p�j���ڂg�B
���������āA�o�g���o�p���`�a�B
��L���ɂ��A�o�a�{�g�a�f���`�a�B�������A�o�g���`�a�Ȃ̂ŁA�o�g�Ƃ`�a�͕��s�ł͂Ȃ�����A�����͐��藧���Ȃ��B
�a�f�g���a�f�p�Ȃ̂ŁA�o�a�{�p�a�f���`�a�B
���F�p���ӂa�f�b��A�ӂ`�a�f��ȊO�ŁA�p�Ƃ`�́A�����o�a�f�̓�����
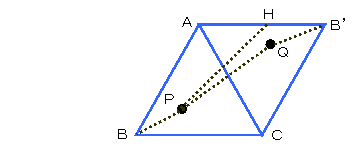
�_�g���A�a�f�g���a�f�p�ƂȂ�悤�ɁA�ӂ`�a�f��ɂƂ�B
���o�p�g�ɂ����āA�ڂp���i�ڂa�f�p�g�̕�p�j���i�ڂa�f�g�p�̕�p�j���ڂg�B
���������āA�o�g���o�p���`�a�B
��L���ɂ��A�o�a�{�g�a�f���`�a�B�������A�o�g���`�a�Ȃ̂ŁA�o�g�Ƃ`�a�͕��s�ł͂Ȃ�����A�����͐��藧���Ȃ��B
�a�f�g���a�f�p�Ȃ̂ŁA�o�a�{�p�a�f���`�a�B
���F�p���ӂa�f�b��A�ӂ`�a�f��ȊO�ŁA�p�Ƃb�́A�����o�a�f�̓�����
��L���ɂ����āA�_�`�Ɠ_�b�����ւ���悢�B
��
�藝�R�̌n�P�F�����̓����傫���̐��O�p�`���A�ӂ�ڂ��ĘA�Ȃ��Ă��āA�e���O�p�`�ɂP�_�����z�u����Ă���A�_�Ԃ̋��������O�p�`�̕Ӓ��ȏ�A�ڂ���ӂɂQ�_���z�u����ĂȂ��Ȃ�A���̐��O�p�`��̗��[�̐��O�p�`�̒��_���炻���ɔz�u����Ă���_�܂ł̋����̘a�́A���O�p�`�̕Ӓ��ȉ��ł���B
���Ƃ��A���}�ł́A�p�a�{�o�`���i���O�p�`�̕Ӓ��j�B
�܂��A�����œ��������藧�Ƃ��́A�_�ԋ����̍ŏ��l�͐��O�p�`�̕Ӓ��Ɉ�v����B
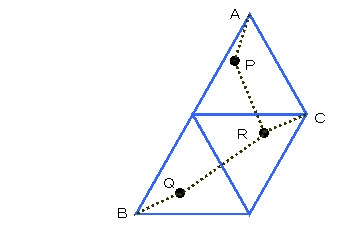
�ؖ��F
��}�̏ꍇ�ŁA��������B
�藝�R����p�a�{�q�b���i���O�p�`�̕Ӓ��j�B
�܂��A�藝�P����o�`���q�b�B
����炩��A�p�a�{�o�`���i���O�p�`�̕Ӓ��j�B
�����œ��������藧�Ƃ��́A�o�`���q�b�A���������Ăo�q���i���O�p�`�̕Ӓ��j�̂Ƃ��ł���̂ŁA�_�ԋ����̍ŏ��l�͂o�q�ƂȂ�B
���O�p�`�̐����������ꍇ�́A���l�ȋc�_�ŁA��菭�Ȃ����O�p�`�̏ꍇ�ɊҌ��ł���̂ŁA���O�p�`�̐��������ł�������B
��
�Ȃ��A�����Łu���������藧�Ƃ��v�́A�u�O�p�`�̒��_�ɔz�u�����v�ƌ��������Ȃ邪�A����͔��Ⴊ����B���}�̂悤�ɁA��`�܂��͕��s�l�ӌ`�ɐ��O�p�`����ׁA���̋��L���Ȃ��ӏ�ɔz�u����悢�B
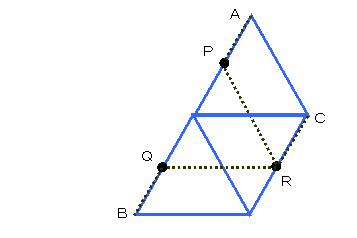
��`�ł����s�l�ӌ`�ł��Ȃ����ו����ƁA�u���O�p�`�̒��_�ɔz�u�����v�͌������������A���̂Ƃ���ؖ��͂ł��Ă��Ȃ��B���Ƃ��Ή��}�̏ꍇ�Ȃ�A������B
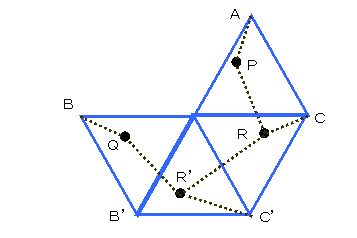
�o�`���q�b�A�o�q���`�b�A�q�͂b�b�f��ƂȂ邪�A�q���b�A�q���b�f���ƁA�q�f�������Ă��܂��̂ŁA�q�͒��_�ɔz�u����˂Ȃ�Ȃ��B
�������A�����ƈ�ʓI�ȏꍇ�͂ǂ��Ȃ̂��A�悭������Ȃ��B
�藝�R�̌n�Q�F���̂悤�ȁA�����傫���̐��O�p�`����Ƃ���B
�@�@�ׂ̐��O�p�`�Ƃ́A���_���邢�͕ӂŐڂ���
�A�@�ׂ̐��O�p�`�ƒ��_�Őڂ���ꍇ�́A���Ηׂ̐��O�p�`�Ƃ́A���̒��_�̑ΕӂŐڂ���B
�B�@���ׂĂ̐��O�p�`�ɂP���_���z�u����Ă���B
�C�@�_�Ԃ̋����́A���O�p�`�̕Ӓ��ȏ�ł���B
�D�@�ׂ̐��O�p�`�����ɂ��ǂ��āA���ɖ߂邱�Ƃ��ł���B
���̂Ƃ��A�_�Ԃ̋����̍ŏ��l�́A���O�p�`�̕Ӓ��ɓ������B
�܂��A���_�Őڂ��鐳�O�p�`�ɔz�u���ꂽ�Q�_�Ƃ��̒��_�Ƃ́A���꒼����ɂ���B
�ؖ��F
���_�Őڂ��鐳�O�p�`�ɒ��ڂ���B
���̂悤�Ȑ��O�p�`�ɔz�u���ꂽ�_�Ԃ̋����́A����ɂ�萳�O�p�`�̕Ӓ��ȏ�ł���B
����ɁA�������̒��_�Ɋ�蓹�����ꍇ�̓��̂�́A������邱�Ƃ͂Ȃ��B
���������āA���������v�������̂́A�i�����̐��O�p�`�̐��j�~�i���O�p�`�̕Ӓ��j�ȏ�ƂȂ�B
�������̂��A�ʂ̌����Ōv�Z����B
����̐��O�p�`����A�ӂŐڂ��鐳�O�p�`�����ǂ��Ă����ƁA���_�Őڂ��鐳�O�p�`�ɂ��ǂ蒅���i���ɖ߂邱�Ƃ����肤�邪�A���̏ꍇ���藝�Q�̌n�P�ɂ��A�_�Ԃ̍ŏ����������O�p�`�̕Ӓ��ɓ��������Ƃ͌����Ă�j�B
�����ŁA���ǂ蒅�������_�Őڂ��鐳�O�p�`�̂����A��O���̂��̂ɔz�u����Ă���_�Ƃ��̒��_�Ƃ̋����ƁA�o���_�̐��O�p�`�ɔz�u���ꂽ�_�Ƃ��̒��_�Ƃ̋����̘a�́A�n�P�ɂ��A���O�p�`�̕Ӓ��ȉ��ł���B
���������āA���̂悤�Șa�����ׂč��v�������̂́A�i�����̐��O�p�`�̐��j�~�i���O�p�`�̕Ӓ��j�ȉ��ł���B
�������āA�܂������������̂̈���́u�i�����̐��O�p�`�̐��j�~�i���O�p�`�̕Ӓ��j�ȏ�v�A��������́u�i�����̐��O�p�`�̐��j�~�i���O�p�`�̕Ӓ��j�ȉ��v�ƂȂ�B���̂��Ƃ́A����炪�u�i�����̐��O�p�`�̐��j�~�i���O�p�`�̕Ӓ��j�v�Ɉ�v���邱�Ƃ������Ă���B
���̂��߂ɂ́A���_�Őڂ��鐳�O�p�`�ɔz�u���ꂽ�_�Ԃ̋����́A���O�p�`�̕Ӓ��ȉ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B
���̋����́A����ɂ�萳�O�p�`�̕Ӓ��ȏ�ł��邩��A���ꂪ���O�p�`�̕Ӓ��Ɉ�v���邱�Ƃ��������B
���̂Ƃ��A�u�������_�Ɋ�蓹�������̂�v�Ɓu�܂������s���������v�Ƃ��������̂ł��邩��A�����̓_�ƒ��_�́A���꒼����ɂȂ���Ȃ�Ȃ��B
��
�� ���̌n�𗘗p����ƁA�藝�Q�̂��́A���̂悤�ɂ��ؖ��ł���B
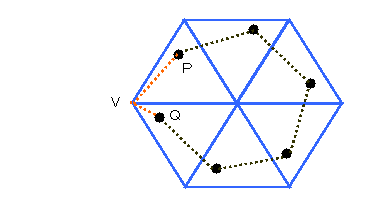
���̌n�ɂ��A��}�̂o�u�p�͓��꒼����B����́A�o���邢�͂p���u�Ɉ�v����Ƃ��Ɍ���B���̂Ƃ��A�p���邢�͂o�́A���Z�p�`�ׂ̗̒��_�ɂȂ�B
���̒��_�ɂ��Ă����ׂē��l�B
��
�藝�S�F�P�ӂ����A���̕ӂ������ŁA�P���p��60���̕��s�l�ӌ`�ɂ́A���X�Q�i���{�P�j�_���z�u�ł���B�������A�z�u����_�̑��݂̋����́A���ȏ�Ƃ���B
�܂��A�z�u����_�̑��݂̋�����������Ƃ���ƁA���X�Q���_���z�u�ł���B
�ؖ��F
���̕��s�l�ӌ`�́A�Ӓ������̐��O�p�`��ɕ����ł��A���O�p�`��ƂȂ�B
���̂Ƃ��A���O�p�`�̌��́A�Q���ł���B
�܂��A�\���������B
�z�u����_�̑��݂̋��������ȏ�Ƃ����ꍇ�A�����̐��O�p�`�̑S���_�ɓ_��z�u���邱�Ƃɂ���āA�Q�i���{�P�j�_���z�u�ł���B
�܂��A�z�u����_�̑��݂̋�����������Ƃ����ꍇ�A���Ƃ��Β��ӏ��60���̒��p���炓�i�Q���{�P�j�^�i�Q���|�P�j�������Ĕz�u����A�Q���_���z�u�ł���i���}�́A�����S�̗�j�B
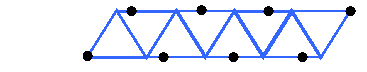
���ɁA�����葽���̓_���z�u�ł��Ȃ����Ƃ������B
�z�u����_�̑��݂̋��������ȏ�Ƃ����ꍇ�A���̐��O�p�`��̂P�[�̐��O�p�`�͂R���_���܂݁A���̐��O�p�`�͂P���_�݂̂��܂ނ��̂Ƃ���i���}�́A�����S�̗�j�B
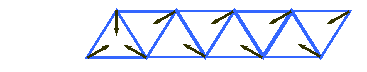
���̂Ƃ��A�R���_���܂ސ��O�p�`�ɂ͍��X�R�_�����z�u�ł����A���̐��O�p�`�ɂ͍��X�P�_�����z�u�ł��Ȃ��B���������āA���v�R�{�i�Q���|�P�j���Q���{�Q���Q�i���{�P�j�_�����z�u�ł��Ȃ��B
�z�u����_�̑��݂̋�����������Ƃ����ꍇ�A�e���O�p�`�ɂ́A���X�P�_�������z�u�ł��Ȃ��B���������āA���O�p�`�̌��i���Q���j���Ĕz�u���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
��
�藝�S�̌n�P�F��ꂪ�����A���ꂪ�i���{�P�j���A�r�����̓��r��`�ɂ́A���X�Q���{�R�_���z�u�ł���B�������A�z�u����_�̑��݂̋����́A���ȏ�Ƃ���B
�܂��A�z�u����_�̑��݂̋�����������Ƃ���ƁA���X�Q���{�P�_���z�u�ł���B
�ؖ��F
���̓��r��`�́A�Ӓ������̐��O�p�`��ɕ����ł��A���O�p�`��ƂȂ�B
���̂Ƃ��A���O�p�`�̌��́A�Q���{�P�ł���A�藝�S�̕��s�l�ӌ`�ɁA�Ӓ������̐��O�p�`��lj��������̂ł���B
�܂��A�\���������B
�z�u����_�̑��݂̋��������ȏ�Ƃ����ꍇ�A�����̐��O�p�`�̑S���_�ɓ_��z�u���邱�Ƃɂ���āA�Q���{�R�_���z�u�ł���B
�܂��A�z�u����_�̑��݂̋�����������Ƃ����ꍇ�A���}�Ɏ���Q�_���A����������Q�f�Ɉړ������邱�Ƃɂ��AP�_���z�u�ł��A�藝�S�����P�_�����z�u�ł���B���Ȃ킿�A�Q���{�P�_���z�u�\�ł���B
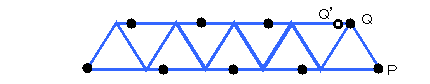
���ɁA�����葽���̓_���z�u�ł��Ȃ����Ƃ������B
�z�u����_�̑��݂̋��������ȏ�Ƃ����ꍇ�A���̐��O�p�`��̂P�[�̐��O�p�`�͂R���_���܂݁A���̐��O�p�`�͂P���_�݂̂��܂ނ��̂Ƃ���i���}�́A�����S�̗�j�B
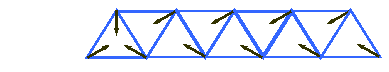
���̂Ƃ��A�R���_���܂ސ��O�p�`�ɂ͍��X�R�_�����z�u�ł����A���̐��O�p�`�ɂ͍��X�P�_�����z�u�ł��Ȃ��B���������āA���v�R�{�Q�����Q���{�R�_�����z�u�ł��Ȃ��B
�z�u����_�̑��݂̋�����������Ƃ����ꍇ�A�e���O�p�`�ɂ́A���X�P�_�������z�u�ł��Ȃ��B���������āA���O�p�`�̌��i���Q���{�P�j���Ĕz�u���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
��
�藝�S����т��̌n�́A�P�̐��O�p�`�ɁA���������傫���̐��O�p�`��lj����Ăł����}�`�ɂ��Ă̂��̂ƍl���邱�Ƃ��ł���B�����ŁA���炽�߂āA���̂悤�Ȑ}�`���u���O�p�`��v�ƌĂԂ��Ƃɂ���B�����܂ł��������A�����̐��O�p�`�́A���O�p�`�i�q�̐��O�p�`�ł���B�Q�̐��O�p�`�����L�_�����Ƃ��́A�ǂ���̐��O�p�`�ɂƂ��Ă����_�ł���_�����L����B
���Ƃ��A���}�̂��̂́A���s�l�ӌ`�ł���`�ł��Ȃ����A�藝�S�₻�̌n�Ɠ��l�Ȑ��������B
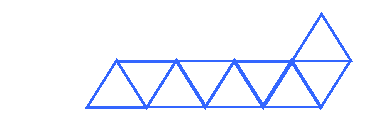
�z�u����_�̑��݂̋����𐳎O�p�`�̕Ӓ��ȏ�Ƃ����ꍇ�A���L�̂��Ƃ�������B
���O�p�`��́A�����lj����鐳�O�p�`���A����܂ł̐��O�p�`�ƁA�K�����傤�ǂQ���_�����L����悤�ɂł���Ȃ�A�i���O�p�`�̐��{�Q�j�̓_���z�u�ł��A���̂Ƃ��͐��O�p�`�̑S���_���߂�B
�����lj����鐳�O�p�`���A����܂ł̐��O�p�`�ƁA�R���_�����L����̂����X�P��ɂł���Ȃ�A���O�p�`�̒��_�̑����i�d���͂P�Ɛ�����j���A�_��z�u�ł���ő�l�ƂȂ�A���̂Ƃ��̔z�u�́A�S���_�ƂȂ�B
�������A�R���_�����L���鐳�O�p�`���K���Q�ȏ�ł��Ă��܂��ꍇ�́A���̂Ƃ���A�ǂ̂悤�ɔz�u�ł��邩�������Ȃ��B�����A���O�p�`�̒��_�̑������Ĕz�u�ł����͌������ĂȂ����A���O�p�`�̑S���_���߂�z�u�ȊO�̔z�u���������Ă��Ȃ��B�ő�l���K�����O�p�`�̒��_�̑����Ɉ�v���A���̂Ƃ��̔z�u�͐��O�p�`�̑S���_�ɂȂ邱�Ƃ�������A�y��P�z�́A�����ɉ�����B
�R���_�����L���鐳�O�p�`���P�����ɂł���ꍇ�́A���O�p�`�̑S���_�ɔz�u�����ꍇ���ő�l�ƂȂ邱�Ƃ�������B��L���藝�Q�́A���̗�ł���B