【問1】(〜以上〜)
【解】kの最大値は10(=(n+1)(n+2)/2)である。
10点が可能であることはすでに言えているので、11点が不可能であることを言う。
正三角形の各辺の3分点どうしを結ぶことによって、辺長が1/3の、9つの小正三角形に分けることができる。このとき、頂点がどの小三角形に属するかを厳密に決める(辺は、端点を除き、接する両小三角形で共有するとしてよい)。
具体的には、下図のようにする。中央の点以外の頂点は、各小三角形に1つずつ属し、中央の頂点だけが、1つの小三角形に属す。

このようにすると、中央の頂点を含まない小三角形には2点を配置することはできない。なぜなら、三角形に含まれる2点の距離がその三角形の最大辺の長さのときは、この2点はこの辺の両端点に無ければならない(「【問3】【問4】は、n=1のときは完全に解けること」の付記参照)のに、これらの小三角形は頂点を1つしか含んでいない、したがってどの辺も高々1端点しか持たないから。
また、中央の頂点を含む小三角形には、3点を配置することはできない。なぜなら、これらの小三角形は、頂点を2つしか含んでいないから。
こうして、配置できる点は、中央の頂点を含む小三角形内に高々2点、他の小三角形内に高々1点ずつ、全部で高々10点となる。
■
【問2】(〜より大〜)
【解】kの最大値は8(=(n+1)(n+2)/2−2)である。
まず、8点が可能であることを言う。
たとえば、下図のように配置する。
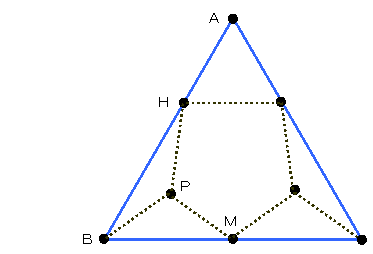
まず、H点をAH=1/3、M点をBM=1/2とし、P点を△HBMの外心とする。
次に、Hを少しずらして、AH=(折れ線AHPBの長さ)/3にし、再度P点を△HBMの外心に移動する。
次に、9点が不可能であることを言う。
正三角形の各辺の3分点どうしを結ぶことによって、辺長が1/3の、9つの小正三角形に分けることができる(境界は共有することにする)。
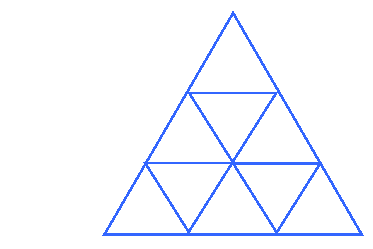
三角形に含まれる2点の距離は、その三角形の最大辺の長さを超えることはできない(「【問3】【問4】は、n=1のときは完全に解けること」の付記参照)ので、いずれの小三角形にも2点以上を配置することはできない。
したがって、各小三角形に1つずつの点を配置することになる。
中央の点を含む6つの小三角形に注目する。
別葉(正三角形列における点の配置の定理2)に示すとおり、このように6つの正三角形が集まっている場合は、互いにその正三角形の辺長より長い距離を離れている点は、5つまでしか配置できない。
したがって、この部分に5つ、他の3つの三角形に1つずつ、合計8つまでしか配置できない。
■