【問1】(〜以上〜)
【解】kの最大値は15(=(n+1)(n+2)/2)である。
15点が可能であることはすでに言えているので、16点が不可能であることを言う。
正三角形の各辺の4分点どうしを結ぶことによって、辺長が1/4の、16個の小正三角形に分けることができる。このとき、頂点がどの小三角形に属するかを厳密に決める(辺は、端点を除き、接する両小三角形で共有するとしてよい)。
具体的には、下図のようにする。中央の小三角形以外は1つずつ頂点を持ち、中央の小三角形だけが頂点を持たない。
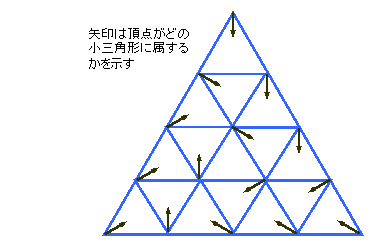
このようにすると、いずれの小正三角形にも2点を配置することはできない。なぜなら、三角形に含まれる2点の距離がその三角形の最大辺の長さのときは、この2点はこの辺の両端点に無ければならない(「【問3】【問4】は、n=1のときは完全に解けること」の付記参照)のに、これらの小正三角形は頂点を高々1つしか含んでいない、したがってどの辺も高々1端点しか持たないから。
小正三角形の数は16個、配置すべき点の数も16個なので、各小正三角形にちょうど1点ずつ配置することとなる。
中央の小正三角形と、元の正三角形の頂点を含む小正三角形を除く、12個の小正三角形に注目する。
これらの小正三角形は、辺で接する小正三角形が2つずつあり、それを順にたどっていくと、出発点の小正三角形に戻るように配置されている。
このような場合、別葉(「正三角形列における点の配置」の定理2の系1)に示すように、配置される点はすべてこれらの小正三角形の頂点にあるか、そのうちの2点が、ある接する辺の両端点になる。
前者の場合は、元の正三角形の頂点を除く頂点がちょうど12個あるので、中央の小正三角形の頂点の位置にも、他の小正三角形に配置されるべき点が配置される。
後者の場合も、そのような辺は、どちらかの端点が、中央の小正三角形の頂点になっているので、中央の小正三角形の頂点の位置に、他の小正三角形に配置されるべき点が配置される。
すると、中央の小正三角形に配置されるべき点をどこにとっても、距離が1/4に満たないので、配置できない。
■
【問2】(〜より大〜)
【解】kの最大値は13(=(n+1)(n+2)/2−2)である。
まず、13点が可能であることを言う。
たとえば、下図のように配置する。
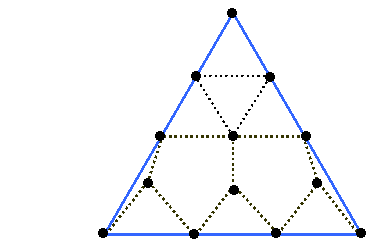
点線は、点間最小距離を実現しているところである。
証明は略す。
次に、14点が不可能であることを言う必要がある。
n≦3のケースからの類推で、正三角形の各辺の4分点どうしを結ぶことによって、辺長が1/4の、16個のの小正三角形に分ける(境界の所属は適当に、一方の小正三角形に所属するようにする)。
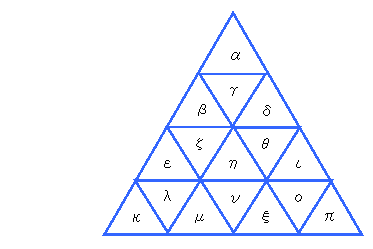
後の検討のため、各小正三角形には、ギリシャ小文字で名前を付けた。
三角形に含まれる2点の距離は、その三角形の最大辺の長さを超えることはできない(「【問3】【問4】は、n=1のときは完全に解けること」の付記参照)ので、いずれの小三角形にも2点以上を配置することはできない。
したがって、各小三角形に高々1つの点を配置することになる。
小三角形の集合で、「辺で接する小正三角形が2つずつあり、それを順にたどっていくと、出発点の小正三角形に戻るように配置されている」という条件のものがいくつかある。それらに配置される点は、別葉(「正三角形列における点の配置」の定理2の系1)に示すことから分かるように、構成小正三角形数より少ない。
具体的には、下記の7つである。
ア. β、γ、δ、θ、η、ζ
イ. η、θ、ι、ο、ξ、ν
ウ. ε、ζ、η、ν、μ、λ
エ. β、γ、δ、θ、ι、ο、ξ、ν、η、ζ
オ. β、γ、δ、θ、η、ν、μ、λ、ε、ζ
カ. ε、ζ、η、θ、ι、ο、ξ、ν、μ、λ
キ. β、γ、δ、θ、ι、ο、ξ、ν、μ、λ、ε、ζ
また、「正三角形列における点の配置」の定理3の系2の条件を満たす小正三角形の集合もいくつかある。これらに配置される点も、構成小正三角形数より少ない(もし構成小正三角形数以上だと、点間距離の最小値は1/4となってしまい、「1/4より大」という題意に反する)。
具体的には、たとえば下記のものがある(他にも多数ある)。
ク. ζ、β、γ、δ、θ、ι、ο、ξ、ν
ケ. ζ、β、γ、δ、ι、ο、ξ、ν
コ. θ、ι、ο、ξ、μ、λ、ε、ζ
サ. β、γ、δ、ι、ο、ξ、μ、λ、ε
ここで、「サ.」について検討する。
ここに並んだ9個の小正三角形の、少なくとも1つは、点が配置されない。それは、βあるいはγであるとしても、一般性を失わない。
さらに、「コ.」を見ると、やはりここに並んだ8個の小正三角形の、少なくとも1つは、点が配置されない。
「コ.」の、点が配置されない小正三角形が、θ、ι、ο、ξのどれかであるとすると、「ウ.」は、β、γ、θ、ι、ο、ξのどれも含まない。「ウ.」も、やはりここに並んだ6個の小正三角形の、少なくとも1つは、点が配置されない。すると、点が配置されない小正三角形が3つ存在することになり、13点しか配置できないことになる。
「コ.」の、点が配置されない小正三角形が、θ、ι、ο、ξ以外、つまり、μ、λ、ε、ζのどれかであるとすると、「イ.」について考えることにより、点が配置されない小正三角形が3つ存在することが分かり、13点しか配置できないことが分かる。
■
蛇足
上記から、14点を配置すると、点間距離の最小値は1/4以下となることが分かるが、さらに、14点配置すると【問1】における配置(15点配置)から1点を除いたものになることも分かる。
たとえば、上記の記号を用いて、ζとθに点が配置されず、他の14個の小三角形に1点ずつ配置されたとすると、β、γ、δ、ι、ο、ξ、ν、μ、λ、εという正三角形列が考えられる。これは、上記サ.に“ν”を追加したものであるが、これを追加したために、οとξは、辺で接しているのでなく、頂点で接しているものと考えることができ、したがって、ο、ξに配置された点の一方は、この頂点でなければならない(【問1】での頂点の所属を踏襲すれば、ξに属することになる)。すると、この列で隣になる小三角形に配置される点の位置も、決まる。こうして順次決めていくと、結局13点しか配置できない。
また、たとえばηとεを除いたものにすると、εに属するεの頂点を15点配置から除いたものになる。